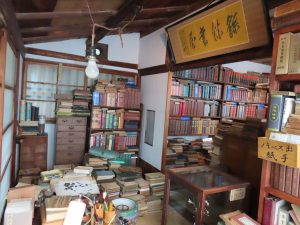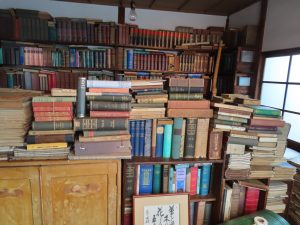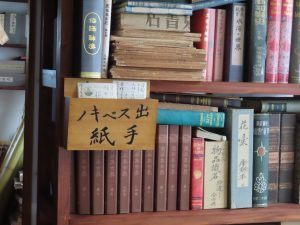こちら名古屋では、きょう、梅雨明けが発表されました。
去年より2週間ほど早いようです。
公園にあった「ナワシログミ その2」をお届けします。
「グミ」は棘(グイ)のある木になる実「グイミ」が
転化しグミとなったそうです。

枝の先は、しばしば棘になります。
葉は互い違いに付き、長さ5~8センチ、
幅2~3.5センチ程の長楕円形です。
縁は不規則に波打ち、乾燥すると裏面に反り返ります。
葉は薄く、表面は深緑色で光沢があり、
側脈が明瞭で裏面からも良く目立ちます。
葉には鱗状毛があります↓
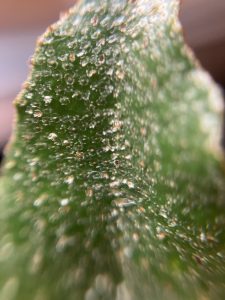
裏面は鱗状毛が密生しており銀白色で、
所々に褐色の鱗状毛があって、
褐色の点々となっています↓

花期は10~11月。
本州(伊豆半島以南)、四国、九州に分布します。
グミ科の植物です。
☆過去記事はこちら→ナワシログミ
★コメントを下さる方へ・・↓
表題をクリックするとコメント欄が現れますので、
そこからコメントして下さいm(_ _)m。
☆本日、mushifab更新しました。
「アカボシゴマダラの夏型」です。
こちらへもお立ち寄りいただけるとうれしいです(*^^*)。