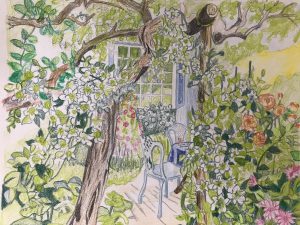きょうは久々にのんびりと家で一日過ごしました。(*^^)v
階下の白梅に蕾がたくさん付いています。
暖冬のせいか、いつもより早く開花してしまった
大きなピンクの椿、「
明石潟」が、もう花を落としています。
きょうは、時々通る道の屋敷まわりにある
「オオイタビ」をお届けします。
大型のイタビカズラということで・・。
「イタビ」は「イヌビワ」の別名で、
イタビのツル性であることから名付けられました。

常緑の匍匐性つる植物です。
葉は艶のある少し厚めの葉で、真冬でも艶々して
綺麗です。
葉は互い違いに付きます。
イチジクのように茎や葉を折ると白い乳液が出ます。

本州の福島県・新潟県以西、四国、九州、沖縄に
分布します。
中部地方では露地栽培可能で、しばしば壁面緑化に
用いられたりもします。
クワ科の植物です。
★表題をクリックするとコメント欄が現れますので、
そこからコメントして下さいm(_ _)m。
☆本日、mushifab更新しました。
「メジロ」です。
こちらへもお立ち寄りいただけるとうれしいです(^^)。